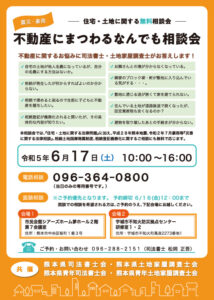NAIANI6月号コラム 遺言とは?遺言書を作成した方がいい方とは?(その1)
今月号は、遺言について説明します。
1 遺言とは?
法律の専門家は“いごん”と読みますが、一般的には“ゆいごん”と読みま
す。自分が死亡した後、残った財産(不動産、現金・預貯金等)をどのように
処分してほしいかという自分の希望を記載する書面です。遺言は民法という
法律で規定されており、記載しなければならないことを書いていない場合、無
効となることがあります。民法にはいろいろな遺言の種類が規定されており
ますが、通常利用するのは、①公証役場で作成する公正証書遺言、②自分で書
いて自宅で保管する自筆証書遺言、③令和2年に始まった自筆証書遺言を法
務局が保管する自筆証書遺言保管制度の3つであると思います。
2 遺言書を作成したほうがよい方とは?
遺言は、自分が亡くなった後、それを相続等で引継ぐ方々が困らないように
する側面と、遺言をする人(「遺言者」といいます。)の希望「このように引継
いでほしい」の側面があります。
引継ぐ方々が困らないようにするための遺言としては、
(1)相続人が多い。
例えば、遺言者が結婚しておらず、配偶者も子どももいない場合、その遺
産はおおよそ遺言者の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が遺言者よ
り先に死亡していると甥姪が相続人となります。残された相続人は、相続人
の数が多く、会ったこともない方々と遺産分割協議を行うことになります。
まとめるのが大変だということはお分かりになられると思います。
(2)相続人同士の仲がよくない。
例えば、自分の子どもである長男と二男の仲が悪い場合、遺産分割協議で
長男と二男が揉めるのは目に見えてますよね。あらかじめ、遺言者が長男と
二男と話し合い、二人の要望を遺言書として残してあげれば、遺言者の死後、
遺言書に従って、相続揉めしないかもしれません。
(3)推定相続人の中に認知症で判断能力のない方がいる。
遺産分割協議書は相続人全員で行わないと効力が生じません。相続人の
中に判断能力がない方がいると、現在の法律ではその方に成年後見人を付
けるか、その方が亡くなるまで待つしかありません。そこで、遺言書を残し
ておけば、遺産分割協議を行う必要はありませんので、その遺言書に書かれ
た内容で相続等ができます。
(4)推定相続人の中に行方不明の方がいる。
上記のとおり、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。そ
の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に対して管理人を選任してもら
う必要があります。その管理人の報酬は30万円は下りません。そこで、遺
言書を残しておくと、遺産分割協議する必要がないのは上記に書いたとお
りです。
来月号はこの続きを書きます。